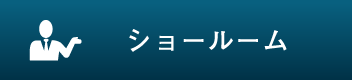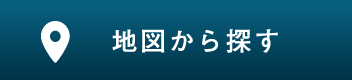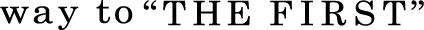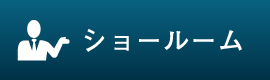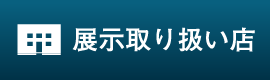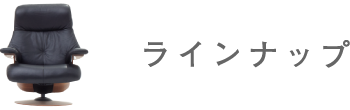人を育て、技を受け継ぐ。
革を、縫う。そこにもまた技がある。
カリモクの工場棟内、試作品とおぼしきモデルが並ぶフロアで一枚の革に手を加える社員。
「革を漉いているんですよ。」
革を縫い合わせ、チェアーの外側を覆う張地を仕立てる。
革を重ねて縫い合わせる部分は、厚みが2倍、3倍になってしまう。
それを防ぐために、縫い合わせる部分だけ予め革を薄く削っておかねばならない。それが、漉くという技だ。
どこまで漉くか、どんな風に漉けばいいかは、作業する人の指先に委ねられている。
同じモデルの張地でも、選ぶ革が違えば当然ながら漉き方は変わる。
経験を積み、感覚で覚えるしかない。

その前に、一枚の革からそれぞれのパーツを切り出さねばならない。
洋服を縫うときと同じように、まずは「型紙」が必要だ。
クッション材を巻いたモデルに素材をあてがい、洋裁の立体裁断さながらに、印をつけながら型をとる。
まるでベテランテーラーの仕事を見ているようだ。
「"型出し"という作業でね、これも慣れないと難しいかな。」
鮮やかにやって見せ、にこやかに説明してくれる、こちらは設計部門のベテラン、I氏。
厚紙で型紙をつくったら図面をデータ化し、型紙そのものは処分する。もったいない気もするのだが。
「データにすればいつでも取り出せますし、基本の型を基に調整もしやすい。 使う素材ごとに寸法を変えないといけませんから。」
一つのモデルに対して、使う張地は革・布合わせて無数にある。
素材ごとに厚さも伸縮性も違うので、同じ図面は一切使えない。
この織り方の布なら、こうなるな。
この厚さ固さの革なら、こうなるな。
素材が持つクセを読めるようになるまで10年はかかった。
「大失敗?ありますよ。図面の通り作ったら裏表が逆になったって、怒られたりねえ」
量産化が決まったら、工場で張地の縫い方を指導するのもI氏の仕事だ。
「ザ・ファーストのような製品はなるべく同じ人に担当してもらいます。
腕が上がって、いい物を速くつくれるようになるからね。」


多くの日本メーカーは職人のカン・コツを数値化して機械化し、人間の作業は、誰でもできるように単純化することで発展してきた。
だがカリモクは、その逆を行っているようにも見える。
「同じものを同じようにつくるならそれでいいんだけど、ウチでは特注品のオーダーが多くて、そうはいかないんです。
ザ・ファーストを買われる方はきっとこだわりが強いから難しい注文がたくさん入るんじゃないかな。
これからが一苦労、二苦労だね。」
そういうI氏の顔はなぜだか嬉しそうだ。
最後には、人の目と手にかなうものはない。
人材を社内でじっくり育てていけば、技術力が廃れることはないのだ。